【はじめに】
重賞競走の歴史を振り返りながら季節の移ろいを感じる「競馬歳時記」。今回は「高松宮記念」の歴史をWikipediaと共に振り返っていきましょう。
高松宮記念は、日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)である。春の古馬スプリントチャンピオン決定戦であるとともに、春のGI競走シリーズの始まりを告げるレースともなっている。
高松宮記念 (競馬)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昭和時代:
1967~1970年:砂2000m「中京大賞典」時代
中京大賞典とは、日本の日本中央競馬会が中京競馬場の砂2000メートル(現在のダートとはやや異なる)で施行していた中央競馬の重賞競走である。
1967年から4回にわたって施行された。1971年も施行予定であった[2]が、高松宮家から優勝杯が下賜されたことを受け「高松宮杯」(のちの高松宮記念)に改められることとなり、第4回競走を最後に廃止された。
中京大賞典
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「高松宮記念」の前身は「高松宮杯」という芝の中距離重賞ですが、更にその前身にあたるレースの「中京大賞典」についても簡単に触れておきます。
1967年、第1回が開催された「中京大賞典」は、当時まだ芝コースがなかった中京競馬場の夏の重賞として創設されます(第3・4回は2月開催)。当時まだレアだったはずですが、当時の出走メンバーをみると「砂(ダート)実績」のある馬も揃っていました。
なお優勝馬のタイヨウは宝塚記念を制して中1週で同レースに出走。初の砂レースへの挑戦でしたが、砂で実績をあげていた古豪・アオバらを3馬身差で完封。翌年以降の砂レースでも勝ち星こそ挙げられませんでしたが、3着以内を外さない適正を見せています。
1968年のミドリエース、1969年のダテホーライも砂に実績のある馬で、非常に固いレースでした。1970年の第4回は「松籟S」と題して京都競馬場の芝2000mで開催され、コダマ産駒の牝馬ファインローズが優勝しています。
1971~1986年:芝2000m【6月】時代
1970年に高松宮宣仁親王から優勝杯が下賜されたのを機に、1971年より「高松宮杯(たかまつのみやはい)」に改称のうえ新設。同年より中京競馬場に新設された芝コースの2000mで、夏の中京開催を飾る中距離の名物競走として施行していた。
高松宮記念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
砂から芝レースに変わったものの、「中距離」というレース形態は1995年まで続きます。この当時の「高松宮杯」は、天皇賞(春)→ 宝塚記念と続く古馬関西の八大競走の約1ヶ月後に開催されており、時期と距離だけでいえば「現代の宝塚記念」と似た位置づけで開催されていました。
第1回から、目黒記念 → 天皇賞(春)→ 宝塚記念と3連勝と勢いに乗り61kgを背負う現4歳馬のメジロムサシが挑戦。シュンサクオーにクビ差敗れたというところから「高松宮杯」の歴史は始まります。そして創設当時から話題性には事欠かないレースでして、
- 第1回(1971年):天皇賞馬メジロムサシが2着惜敗
- 第2回(1972年):天皇賞馬メジロアサマが3着惜敗
- 第3回(1973年):ハマノパレードが落馬により予後不良に
- 第4回(1974年):ハイセイコーが現役最後の勝利
当時は、「宝塚記念」を制した勢いで6月下旬の「高松宮杯」に挑戦するのが普通でした。場合によっては、そのまま夏の北海道に遠征することも珍しくなかったとなれば今のローテーションとは隔世の感がありますね(^^;
そして、昭和50年代に入っても、話題性のある中距離ホースが華々しく春競馬を締めくくっています。
- 第7回(1977年):トウショウボーイが62kgを背負って完勝
- 第11回(1981年):ハギノトップレディが6馬身差の圧勝
- 第13回(1983年):ハギノカムイオーが2馬身半差で勝利
【トウショウボーイ】は、他のメンバーが皆55kgの中、1頭7kgも重い62kgを背負って完勝。そして1980年代に姉弟制覇を果たした【ハギノトップレディ】と【ハギノカムイオー】は、その母親イットーも第5回(1975年)の勝ち馬であり、母子2代で3勝という離れ業を成し遂げています。
平成・令和時代:
1987~1995年:芝2000m【7月】時代
1987年になると、時期が3週間ほど後ろ倒しとなり、7月中旬の開催となります。宝塚記念など中距離の重賞戦線を沸かせた馬たちのうち夏場まで頑張る馬が多かったこの頃、GIIとしてはそれなりに話題性のあるメンバーが揃いました。
- 第19回(1989年):メジロアルダン、6戦連続連対で初重賞制覇
- 第20回(1990年):バンブーメモリー、前年2着のリベンジを59kgで
- 第21回(1991年):ダイタクヘリオス・ダイイチルビー ハナ差決着
- 第24回(1994年):ナイスネイチャ、2年半ぶり重賞制覇(最後の勝利)
- 第25回(1995年):マチカネタンホイザ、2000m時代最後の優勝
など、とにかく懐かしい馬名が並びます。今でいう“札幌記念”と似た好メンバーが揃っていました。(札幌記念は「秋に向けた夏競馬」の印象ですが、この当時の高松宮杯は「春の名残の夏競馬」という印象でしたかね。)
そしてこの時代の代表的な存在が、現3歳当時の【オグリキャップ】の古馬初挑戦です。笠松時代から数えて13連勝を果たすこととなります。※地方競馬からの移籍馬による重賞連勝記録である5連勝達成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1996~1999年:芝1200m【5月】時代
そういった伝統を思い切って改めたのが1996年です。「高松宮杯」という名と中京競馬場で開催されるという以外は殆どの要素が改まりました。
1996年に中央競馬の短距離競走体系が改善・整備され、本競走は距離を芝1200mに短縮のうえ施行時期も5月に変更し、GIに格上げ。これにより、中央競馬のいわゆる「中央場所(中山・東京・京都・阪神)」以外の競馬場で初めて行われる常設のGI競走として、春の短距離王決定戦に位置づけられた。その後、1998年には現名称に改称。
高松宮記念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
実はまだ「短距離」のレースになってからの歴史よりも、前身(砂コース)を含めれば「中距離」競走だった時代の方が長いという事実に驚かされました。
すっかり装い新たに短距離GIとして模様替えをした「高松宮杯(GI・芝1200m)」に、まさかの挑戦として話題を集めたのが3冠馬【ナリタブライアン】でした。
天皇賞(春)2着から転戦して挑んだ高松宮杯を、持てる力を振り絞って完走しますが、短距離適正の高い馬たちに差をつけられてしまっての4着。このレースを最後に現役を引退することとなりました。
- フラワーパーク R1.07.4
- ビコーペガサス 2 1/2
- ヒシアケボノ 1
- ナリタブライアン 1 1/4
5月開催当時は「安田記念」とのレース間隔も短い上に、短距離に実績のある1番人気が勝てない年が続いていましたが、2000年から「3月」開催に移行すると、再び状況が変わってきます。
2000年代:キングヘイローが撫で切った!
2000年代に入っても、GI昇格から2006年までの11回のうち、1番人気はトロットサンダーの2001年以外勝ちきれない時期が続きます。しかし下をご覧頂ければ分かるとおり、人気の一角を占める馬たちが1番人気以下を下して優勝した歴史の積み重ねです。堂々たるスプリンターが名を連ねています。
| 第30回 | 2000年3月26日 | キングヘイロー | 牡5 | 1:08.6 |
| 第31回 | 2001年3月25日 | トロットスター | 牡5 | 1:08.4 |
| 第32回 | 2002年3月24日 | ショウナンカンプ | 牡4 | 1:08.4 |
| 第33回 | 2003年3月30日 | ビリーヴ | 牝5 | 1:08.1 |
| 第34回 | 2004年3月28日 | サニングデール | 牡5 | 1:07.9 |
| 第35回 | 2005年3月27日 | アドマイヤマックス | 牡6 | 1:08.4 |
| 第36回 | 2006年3月26日 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 1:08.0 |
| 第37回 | 2007年3月25日 | スズカフェニックス | 牡5 | 1:08.9 |
| 第38回 | 2008年3月30日 | ファイングレイン | 牡5 | 1:07.1 |
| 第39回 | 2009年3月29日 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 1:08.0 |
個人的に特に印象的だったのは【キングヘイロー】のG1制覇です。「キングヘイローが撫で切った!」という実況を当時聞いて、強烈に痺れたのを覚えています。
2010年代:接戦多き電撃の6ハロン
2010年代に入ると、年によってレースレベルのバラつきが少し目立つ印象ですが、2010年代の前半は「キンシャサノキセキ(2010・11)」、「カレンチャン(2012)」、「ロードカナロア(2013)」という強力なメンバーたちが覇を競っていました。
また、キンシャサノキセキが勝った2010年は1着から「ハナ・クビ・クビ・ハナ」でしたし、2020年は(クリノガウディーが1位入線から4着降着したことを度外視すると)モズスーパーフレアから見て「ハナ・アタマ」差の接戦でした。ちなみにこの時の2着こそが4歳時の【グランアレグリア】です。
そして、2021年はダノンスマッシュ → レシステンシア → インディチャンプと続く複勝圏内は、「クビ・クビ」での接戦。短距離ということ以上に激しいゴール板前の攻防の多いイメージがあります。
また、2015年には香港から挑戦した【エアロヴェロシティ】が4番人気で外国馬初の優勝を果たしていることも申し添えておきましょう。
| 第46回 | 2016年3月27日 | 114.25 | ビッグアーサー | 牡5 | 1:06.7 |
| 第47回 | 2017年3月26日 | 113.50 | セイウンコウセイ | 牡4 | 1:08.7 |
| 第48回 | 2018年3月25日 | 114.50 | ファインニードル | 牡5 | 1:08.5 |
| 第49回 | 2019年3月24日 | 112.75 | ミスターメロディ | 牡4 | 1:07.3 |
| 第50回 | 2020年3月29日 | 117.50 | モズスーパーフレア | 牝5 | 1:08.7 |
| 第51回 | 2021年3月28日 | 115.25 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 1:09.2 |
| 第52回 | 2022年3月27日 | 113.00 | ナランフレグ | 牡6 | 1:08.3 |
| 第53回 | 2023年3月26日 |
最後に、2016年以降のレースレーティングを見ていきましょう。上位4頭の平均レートから算出した値で、国際基準によると「115」がG1の基準とされています。
ここ6年の単純平均は「114.42」です。2020年は117.50まで行きましたが、2022年には再び113.00ポンドまで下がってしまうなど、G1昇格時のハイレベルさは影を潜めてしまいました。
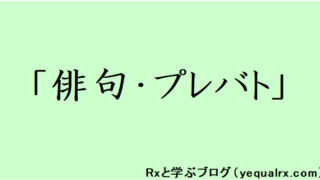
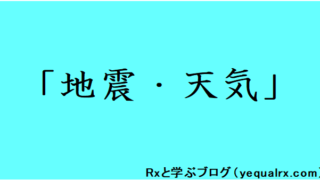
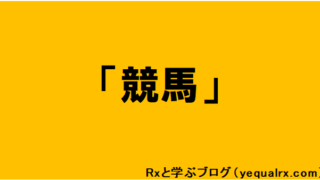
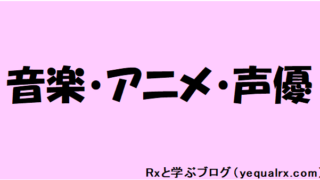
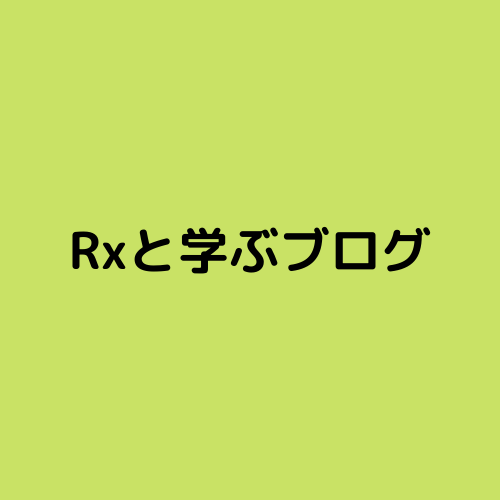

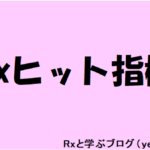
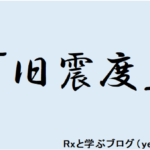
コメント