【はじめに】
重賞競走の歴史を振り返りながら季節の移ろいを感じる「競馬歳時記」。今回は「フラワーC」の歴史をWikipediaと共に振り返っていきましょう。
桜花賞・優駿牝馬(オークス)と続く牝馬クラシック路線の関東地区における前哨戦として位置付けられている。
1987年に創設された、4歳(現3歳)牝馬による重賞競走。施行場・距離は創設時より、中山競馬場の芝1800mで定着している。創設時の負担重量は馬齢だったが、2001年より別定に変更された。
フラワーカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昭和時代:
昭和40年代:条件戦として創設
日本語版ウィキペディアで補足できていない「前史」があるので、本記事ではそこから触れていきたいと思います。上のウィキペディアには「1987年に創設された」と書かれており、その下に重賞の前身にカウントされていない“オープン特別”時代があるとされています(ウィキペディアで触れられているのは1980年以降のみ)。
しかし、netkeiba.com さんのデータベース検索によれば、「フラワーC」という名前のレースは、それより遥か前の昭和40年代には毎年のように開催されていたことが分かります。

これによると1960年代に「条件戦」として創設され、1969年からオープン特別に昇格したという記録が残されています。
気づけば、当時から「中山競馬場」の「芝中距離路線」で開催されていることが分かります。JRAの定義によればこのオープン特別時代は前身にカウントされていませんが、実質的にはこのレースを重賞に昇格させたと見ても良いのではないでしょうか。そして、この時代の活躍馬を探すと、
- 1969年:シャンデリー
次走「4歳牝馬特別」でオークス馬【シャダイターキン】に6馬身差の圧勝。 - 1971年:ヤマアズマ
重賞「クイーンC」に続き連勝。次走「4歳牝馬特別」を最後に現役引退。
この2頭は、その後の活躍を期待される走りを見せるも、本番クラシックで活躍できず引退しました。
昭和50年代:マイルから距離延長
発足当時は1600mのマイル戦だった「フラワーC」ですが、1980年代に入ると距離が1800m→2000mと伸びます。なお、マイル戦時代には、後に牡馬混合重賞を制覇する牝馬を3頭も輩出していました。
- 1978年:マイエルフ
生涯48戦9勝2着9回、1年半後「福島記念」を制覇 - 1980年:ジュウジアロー
3歳:牝馬東京タイムズ杯
4歳:新潟大賞典、毎日王冠(レコード勝ち)
5歳:京王杯オータムH、カブトヤマ記念 ※当時牝馬最高賞金 - 1981年:エイティトウショウ
ラジオたんぱ賞、金杯(東)、中山記念(連覇)
牝馬クラシック戦線には縁遠い馬たちですが、タフや牡馬混合重賞を制する馬がこれだけいるという渋さは開催形態の違う当時から変わらない傾向だったのかも知れませんね、興味深いです。
昭和60年代:1800mに短縮、重賞(GIII)昇格
1985年(昭和60年)になると開催時期が半月前倒しされ3月中旬となります。そして、1987年(昭和62年)にようやく(実質創設20年にして)重賞(GIII)に昇格を果たします。このタイミングで、現在の芝1800mに再短縮されます。
重賞になっての第1回「ハセベルテックス」は桜花賞4着、第2回「フリートーク」は桜花賞3着と、時期を前倒しして距離を短縮した効果が如実に出てか、クラシック戦線への結びつきが強まった印象の出だしとなりました。
平成・令和時代:
1990年代:ホクトベガ、シーキングザパールなどを輩出
平成1桁台には、オープン特別(昭和50年代)にも負けず劣らずの名馬達を輩出するようになります。しかしこれはオープン特別時代を含めると、「フラワーC」がいきなり登竜門になったというよりかは着実に実質的な前身レースの個性を受け継いだと見るべきかと思います。
- 1990年:ユキノサンライズ
4歳時、中山牝馬S → 中山記念と連勝 - 1993年:ホクトベガ
芝ではエリザベス女王杯、札幌記念、現6歳時にはダート8戦8勝 - 1994年:ヒシナタリー
下半期に小倉記念、ローズS、阪神牝馬特別と重賞3勝 - 1997年:シーキングザパール
フラワーCが重賞3勝目、後にNHKマイルCとモーリスドギース賞とGI2勝
以上はもう牡馬を相手に堂々たるレースを見せていました。下の2頭は外国産馬であり、クラシックに出走できない中でその強さを発揮するような存在感をアピールしています。
2000年代:ついにクラシックホースを輩出
1990年代にGI馬を輩出するも、20世紀を通じて優勝馬から「クラシックホース」を輩出するに至らなかった「フラワーC」。しかし、2000年代に入ってついにその悲願が叶います。
- 2002年:スマイルトゥモロー
4番人気でオークス制覇(同レース勝ち馬では史上初) - 2004年:ダンスインザムード
3連勝で同レース制覇、4連勝(無敗)で桜花賞制覇 - 2005年:シーザリオ
桜花賞2着の後、日米オークス制覇の偉業 - 2006年:キストゥヘヴン
6戦連続連対、3連勝で桜花賞制覇 - 2008年:ブラックエンブレム
春はオークス4着が最高も、秋華賞を11番人気で制覇
10年で5頭のGI馬を輩出するという絶頂期を迎えます。正式に「トライアルレース」として位置づけられているレースよりも、1800mという距離が“真価”を問われるような舞台設定なのかも知れませんね。
しかし徐々に、平成20年代に入った頃から緩やかに活躍馬の輩出度合いが落ちることになります。
2010年代:桜花賞とのレース間隔が……
2010年は桜花賞2着となるオウケンサクラが勝利、フラワーC3着のサンテミリオンがアパパネと同着でオークスを制覇しますが、その後は勝ち馬からGI馬を輩出できていません。
個人的には、昭和の時代から設定されてきたレース条件のうち、「中山芝1800m」は良いのですが、「3月後半の開催」というのが「桜花賞」とのレース間隔が短く、少しずつ回避されるようになってきているのではないかと考えます。
ただ、この時代になると、フラワーCで負けた馬の中から、桜花賞を回避してその後にGI馬になる馬が複数出ています。その意味では将来性のあるレースといえるかも知れません。例えば、
- 2014年:ショウナンパンドラ 1番人気5着
3歳時:秋華賞、4歳時:ジャパンC制覇 - 2016年:ヴィブロス 10番人気12着
3歳時:秋華賞、4歳時:ドバイターフ - 2018年:ノームコア 4番人気3着
4歳時:ヴィクトリアマイル、5歳時:香港C - 2021年:ユーバーレーベン 1番人気3着
3歳時:オークス
こういった馬たちが活躍を見せています。令和に入ってからはユーバーレーベンがフローラS3着からオークスに向かい、ソダシらを下して2勝目をGI制覇で果たしています。
では、直近7年(2016年以降)のレーティングをみていきましょう。牡馬混合戦と揃える意味で、本来の値に+4ポンドの調整を行っています。
| 第30回 | 2016年3月21日 | 104.75 | エンジェルフェイス | 1:49.3 |
| 第31回 | 2017年3月20日 | 105.75 | ファンディーナ | 1:48.7 |
| 第32回 | 2018年3月17日 | 109.50 | カンタービレ | 1:49.2 |
| 第33回 | 2019年3月16日 | 108.25 | コントラチェック | 1:47.4 |
| 第34回 | 2020年3月20日 | 107.50 | アブレイズ | 1:48.2 |
| 第35回 | 2021年3月20日 | 109.25 | ホウオウイクセル | 1:49.2 |
| 第36回 | 2022年3月21日 | 109.00 | スタニングローズ | 1:48.5 |
2016・2017年のレースレーティングは、「G3の基準:105」ギリギリでした。その後は何とか水準を回復していて、平成30年台以降に限れば、寧ろ「G2の基準:110」に近づいています。2022年には、秋に紫苑S → 秋華賞を制する【スタニングローズ】が勝って久々に勝ち馬からG1馬を輩出しています。
しかし、前述のとおり、桜花賞まで期間が短いことを鑑みると、オークスに向けた意識の高い一流馬が挑戦しない場合、レースレベルが著しく低下することも懸念されます。こちらもレース時期がこのままで良いのかを将来検討すべき時代が来るのかも知れません。
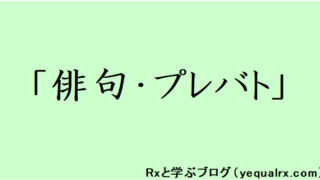
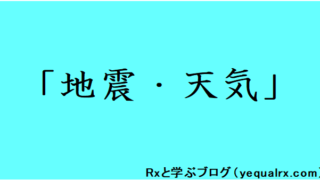
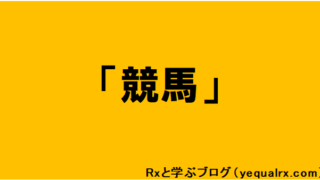
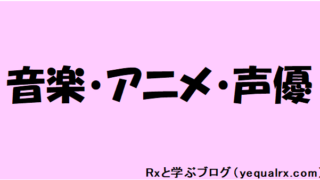
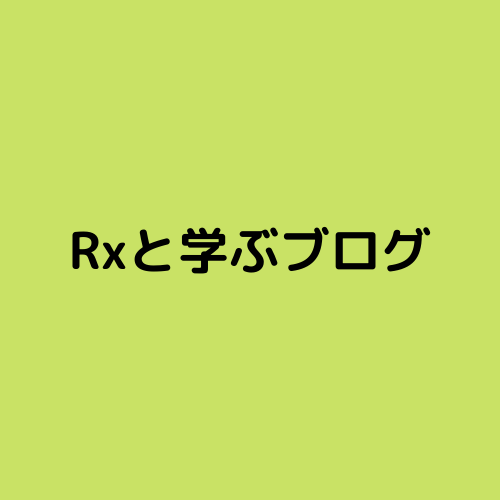



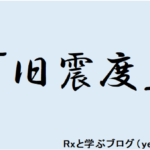
コメント