【はじめに】
この記事では、気象官署「仙台管区気象台」で観測された過去の強烈な揺れをまとめていきます。
独自指標である「旧震度」について、上の記事で纏めていますので興味を持たれた方はぜひ上記リンクから合わせてご覧ください。
仙台管区気象台のHPにみる沿革
まずは、気象庁「仙台管区気象台」のホームページから、「沿革」というページを引用します。

宮城県内のもうひとつの観測点「石巻」でも触れましたが、歴史は「石巻」の方が遥かに古く明治時代まで遡り、「仙台」は大正の終わりに設立したため、まだ100年に達していないという状況です。
1939年に「地方気象台」、1949年には「管区気象台」に昇格しますが、昭和1桁台までは「宮城県立石巻測候所仙台出張所」という位置づけでした。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
震度1以上(有感地震)は年に数十回程度
まずは、気象庁の「震度データベース検索」で、震度1以上(有感地震)の10年ごとの観測回数を表にしてみました。(↓)
| 期間 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920年代 | 19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1930年代 | 122 | 80 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 243 |
| 1940年代 | 81 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 1950年代 | 99 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 1960年代 | 150 | 60 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| 1970年代 | 132 | 56 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 205 |
| 1980年代 | 113 | 54 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 1990年代 | 125 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2000年代 | 189 | 66 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 273 |
| 2010年代 | 846 | 265 | 84 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1208 |
| 合計 | 1876 | 715 | 227 | 41 | 8 | 0 | 2 | 2869 |
・地震の発生日時 : 1920/01/01 00:00 ~ 2019/12/31 23:59
・観測された震度 : 仙台宮城野区五輪 で 震度1以上 を観測
・地震回数の集計 : 年代別回数
「東日本大震災」以前は、およそ10年で100~200回台となっています。2000年代以前は、およそ年に十数回ですから月に1~2回程度が平均値だったと思われます。
しかし、2010年代には1,000回超、2011年だけでも714回もの有感地震が観測され、2014年以降は、約50回程度と平均して週1回程度に落ち着いてしまっています。
震度4(中震)以上:50回あまり
そして、震度4(中震)以上に限定すると、昭和以降(~2021年度)で56回観測しています。単純に均してしまうと「2年に1回」程度となりますが、実際には本震-余震の形を取って纏まって発生することも珍しくないため、10年近く観測されないといった時期もかつてはありました。
例えば、1930年代は8回、1960年代は7回、2000年代は6回、2010年代は13回(うち2011年だけで9回)観測している一方で、1940年代は1回のみなど、時期によってバラツキが大きいのも特徴です。
改めて地域としてみると、「房総沖地震」、「新潟地震」、「東北地方太平洋沖地震」の3例を除き、全て日本海溝の陸地側(太平洋沖から本州内陸部)に集中していることが分かりますね。
震度5(強震)以上:約80年で13回
そして気象庁の観測で「震度5(強震)以上」は、1933年の「昭和三陸地震」以来の約80年間で13回に達しています。観測方法の変更があったとはいえ、2005年からの約20年間で7回を観測しているのは、やはり日本海溝沿いでの地震活動が活発化していることを表している印象です。
| 地震の発生日時 | 震央地名 | 深さ | M | 最大震度 | 「仙台」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933/03/03 02:30:47.6 | 三陸沖 | 0 km | 8.1 | 震度5 | 震度5 |
| 1936/11/03 05:45:57.1 | 宮城県沖 | 61 km | 7.4 | 震度5 | 震度5 |
| 1938/11/05 17:43:18.4 | 福島県沖 | 43 km | 7.5 | 震度5 | 震度5 |
| 1938/11/05 19:50:14.9 | 福島県沖 | 30 km | 7.3 | 震度5 | 震度5 |
| 1964/06/16 13:01:40.7 | 新潟県下越沖 | 34 km | 7.5 | 震度5 | 震度5 |
| 1978/06/12 17:14:25.4 | 宮城県沖 | 40 km | 7.4 | 震度5 | 震度5 |
| 2005/08/16 11:46:25.7 | 宮城県沖 | 42 km | 7.2 | 震度6弱 | 震度5弱 |
| 2008/06/14 08:43:45.3 | 岩手県内陸南部 | 8 km | 7.2 | 震度6強 | 震度5弱 |
| 2011/03/11 14:46:18.1 | 三陸沖 | 24 km | 9.0 | 震度7 | 震度6弱 |
| 2011/04/07 23:32:43.4 | 宮城県沖 | 66 km | 7.2 | 震度6強 | 震度6弱 |
| 2021/02/13 23:07:50.5 | 福島県沖 | 55 km | 7.3 | 震度6強 | 震度5強 |
| 2021/03/20 18:09:44.8 | 宮城県沖 | 59 km | 6.9 | 震度5強 | 震度5弱 |
| 2022/03/16 23:36:32.6 | 福島県沖 | 57 km | 7.4 | 震度6強 | 震度5強 |
・地震の発生日時 : 1919/01/01 00:00 ~ 2022/03/31 23:59
・観測された震度 : 仙台宮城野区五輪 で 震度5弱以上 を観測
・検索結果地震数 : 13 地震 (「地震の発生日時の古い順」で検索)
2021年3月の地震は、速報値から下方修正されてM7を下回りましたが、その他の地震は全て大地震(M7以上)といえる規模を持っており、強烈な揺れをもたらす地震でもありました。
最近では、2021年から2022年にかけて3度、震度5弱以上の地震が観測されましたが、これも決して良くある話しではなくて、2年間に3回というのは1930年代をも上回る記録的なことだったと言えそうです。
震度6弱:2011年に2回
上記の表にもある通り「仙台」で「震度6弱」を観測した2例は、いずれも2011年に起きたものです。1例目は「東日本大震災」を引き起こした超巨大地震。そして、その翌月7日の深夜に起きた宮城県沖を震源とする大地震(最大震度6強)で、「仙台管区気象台」でも震度6弱を観測しています。
もちろん、気象庁震度階級や観測方法の違いがあるため、代表的なところでは「1978年宮城県沖地震」など、大きな建物・人的被害をもたらした地震(当時の階級で最大震度5)についても、今の基準だったならば「震度6弱以上」だった可能性は捨てきれない点には注意が必要かも知れません。あくまでもオフィシャルなデータとしては、「震度6弱」は2011年の2例のみです。
ちなみに、仙台市内でも強烈な揺れとなった上記2例に関しても、小数点1位まで表示した計測震度の値は「5.6」でありました。「震度6下限:5.5」であることも弁えておく必要があろうかと思います。
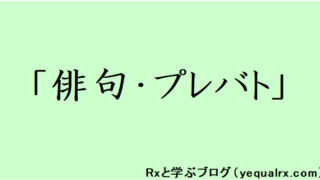
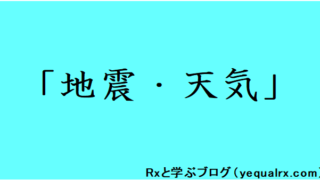
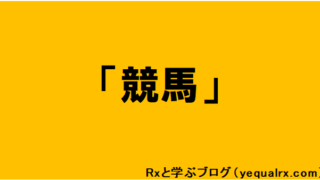
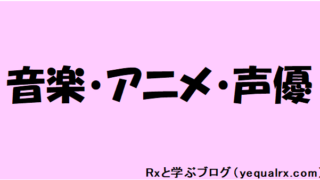
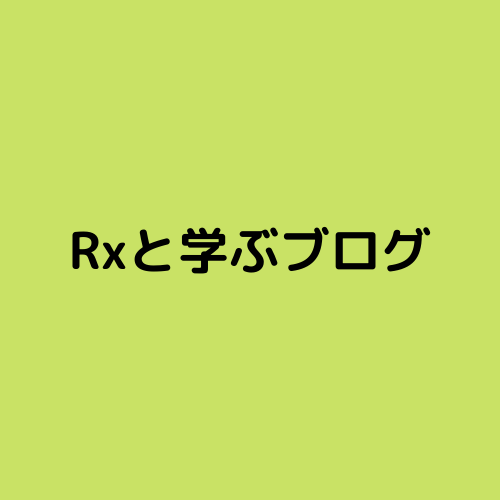

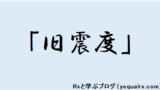



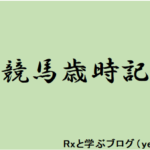

コメント