【はじめに】
この記事では、季語に関するよくある質問の代表格ともいえる『マスクって季語なの?』論争の最前線(イマ)に迫っていきたいと思います。
結論から言ってしまえばまだコロナ禍になって2~3年なので時期尚早となるのでしょうが、なぜそういった答えになるのかというを、昭和の例句から「プレバト!!」の村上名人の句も紹介しながら追っていきたく思います。
ウィキペディアに学ぶ「マスク」という季語
「マスク」の季語的な側面について、日本語版ウィキペディアでは以下のとおり纏められています。
季語としてのマスクは、現代人が一般的に用いる冬季の防寒・防疫用のマスクを指す。全く同じ形のマスクでも花粉症対策や防塵対策に用いる場合、それは季語として扱えず、あくまで防寒・防疫を目的として冬季に用いるマスクのみ該当する。すなわち、マスクは三冬(初冬・仲冬・晩冬の3か月)の季語である。分類は人事/行事/生活。親季語や子季語は無い。
マスク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
端的にまとめられていて分かりやすい説明だと思います。これに関して歴史的経緯をざっくり書くと、
以上の様に(細かくは時代が違う部分もあるでしょうが)トレンドは、平成時代に議論が活発となっていきましたが、何とかマスクが季語という地位を揺るがされずにキープしてきたのでした。
平成の頃なら、夏井いつき先生の語り口調を借りて『実はマスクも季語なんだよねぇ~』とラジオ番組で月曜日(初心者レベル)に紹介されていたかも知れません。そして、まだ「花粉症」が季語としない派が優勢な中で、花粉症や粉塵用のマスクを詠んだ場合は季語と認めないのが主流派でした。
- (小型のものでも)俳句歳時記の冬の季語には、以下のような季語が並んでいます。
- 風邪(かぜ)
- 感冒・流感・流行風邪・インフルエンザ
- 風邪薬
- 咳・しわぶき・嚔・くしゃみ・鼻水・水洟
- 例句をみる限り、高浜虚子らの時代にはこれらを季語として作句されていました。『風邪』を冬の季語とした時に、そこからの連想で『感冒』が季語として定着し、同じく『風邪薬』なども季語として設定。更にそこから『マスク』が自然な流れの中で季語として定着していったのだと思います。
ここまでが平成までの時代の、季語としての『マスク』です。
夏井いつき俳句チャンネルでも話題に
「マスク」が季語として最も注目されたのは、恐らく2020年(令和2年)でしょう。言わずもがな、「コロナ禍」で国民皆マスク状態となったあの騒動の時期です。
春に緊急事態宣言が出され、そういったご時世を振り返る形で注目を集めたのが、2020年12月17日に夏井いつき俳句チャンネルに投稿された動画『【季語】「マスク」は季語として絶滅寸前?』でした。
動画の前半部分は、夏井親子がライフワークとしている『絶滅寸前季語辞典』について。今や使わなくなったりほぼ廃れてしまった季語を纏めた人気の書籍で、10年に1度改定する中で見直しを行っている最中に「コロナ禍」が来たと振り返っています。
一方で、季語は「ナマモノ」であって、『(ユニクロによって復活した)ステテコ』や、『(キャンプブームなどでホームセンターに今でも並んでいる)火吹き竹』などは、(NHKなどの番組に登場した際も触れていた)『復活した季語』の代表格であると熱く語っています。
そして後半に本題の「マスク」に移り、これまで(平成)は、花粉症の国民病となって以降「春のマスク」を冬のマスクと別項に立てたらどうか? という議論や、そうしたら秋にも別の種類による花粉症が多くの人を悩ませるようになり「花粉症」を春だけの季語として良いのか? といったさらなる議論を呼んで俳句界でも意見が分かれて収拾がつかなくなっていたと回想していました。
ここで重要になってくるのが、お2人が7分過ぎに語っていたフレーズです。
夏井『一年中やってるということは、何が起こるかっていうと……?』 家藤『日常目にするものだから、マスクに対して季節感が失われるということですね。』 夏井『そう。マスクそのものがなくなる訳じゃない、たくさん広がってるんだけど、それによって季節感を奪われる。初めてのケースだよね、これね……』
ここで登場してきた「季節感」というのが季語にとっては生命線とも言えるものです。例えば、風邪も咳も厳密には冬に限った話ではありません。一年中あります。しかしそれでも冬の季語と言われると、ある程度の説得力をもって今でも納得できる部分が大きいかと思います。
『月』は一年中ありますが、秋が最も美しいとされますし、『林檎』などの動植物も今はスーパーで一年中並ぶようになりましたが、旬をもって季語として認められてきました。いずれの「季語」も『季節感』というのが分類において非常に大事なファクターとなっているのです。
- 一つ答えが出ているものとして、「ハンカチ」があります。『汗ぬぐい』という夏の季語が『汗』という夏の季語とリンクして掲載されており、その英語名(一部、傍題)として「ハンカチ」が季語として掲載されているものが多くあります。
- 一方で、卒業式などで涙を拭いたり、手を洗った後に手を拭いたりする際の小物としての「ハンカチ」は、『汗』という夏の季語とは独立した存在となっていますから、同じものであっても「季語ではない」という認識が定着しています。
- かつては、『汗』を『インフルエンザ』、『ハンカチ』を『マスク』に置き換えた論法で、風邪対策としてのマスクが冬の季語として認められていたのです。
都会暮らしの人間は特に、『これも季語なの!?』とか『これの旬の時期ってこの季節(だったん)だ!』といった発見があるから「俳句歳時記」は面白い面がある一方で、令和以降に改定される歳時記が最も頭を悩ます季語となったのが、この「マスク」というアイテムなのでしょう。
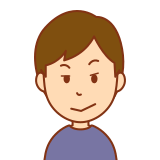
一年中「マスク」をつけている人が増えてきたんだから、もう流石に「冬の季語」と限定するのは時代遅れなんじゃない?
という意見も考えられる一方で、

コロナ禍の前から、「マスク」を冬(風邪菌・ウイルス対策)以外につける人もいた。コロナ禍で一年中つけるようになったのが数年の間だけかも知れないのに、そんなに急いで決めちゃって良いものなのか?
という慎重派の方もいます。そして、俳人の間でも意見が分かれていますが、結構な割合の人が、
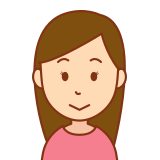
もともと「マスク」が季語になった経緯や、20世紀の例句の歴史を考えると、「マスク」という項自体を思い切って消すことは難しいよね。
と考えているのだと思います。今、季語であるかはあと数年から十数年みないとわかりませんが、少なくとも平成までは「季語」として認識され、作句例が沢山ある訳ですから、その歴史と共に紹介する。紹介するには「マスク」という項を立てなければならないので、結論を保留した形で掲載する形を取る歳時記が令和の時代に増えていくのだと思います。
例えば、2022年(令和4年)に改定された新しい「角川俳句大歳時記」には、しっかりとコロナ禍まで収録されています。大手の歳時記の改訂版でこの方針が示されたことは、少なくとも2020年代の大きな潮流の中で、最適解の一つを提示したという見方もできるでしょう。
これが結論になっていない結論です。そしてこれが多くの俳人にとっての悩ましい中での処世の最適解の一つという共通認識なのではないかと考えるのです。
夏井いつき先生の「俳句ことはじめ」や、下の動画にもあるとおり、季語というのは認定機関がある訳ではなく、最終的に個々人の判断となります。しかもそれは数十年や百年単位で培われるものなので、たった2~3年で結論が出るようなものではないというのが本音なのです。
俳句歳時記と「プレバト!!」にみる『マスク』の例句
日本語版ウィキペディアには、以下の例句が季語「マスク」の例句として掲載されています。いずれも昭和中盤までの作句例であり、特に戦後の句には季語に分類されうるものが複数入っているものも清濁併せ呑むように引用されてしまっています。
マスク
- マスクして 我と汝でありしかな ──高浜虚子『五百五十句』(1943年/昭和18年刊)所収。 1937年(昭和12年)1月23日発句。
- マスクして マスクしている人にあう ──細井啓司(昭和初期)
- マスクして しろぎぬの喪の夫人かな ──飯田蛇笏『春蘭』(1947年/昭和22年刊)所収
- 新しきガーゼのマスク 老婦人 ──京極杞陽『くくたち』下巻(1947年/昭和22年刊)所収
- 純白のマスクぞ深く受験行 ──岸風三楼『往来』(1949年/昭和24年刊)所収
- マスクして 北風を目にうけてゆく ──篠原梵『雨』(1953年/昭和28年刊)所収
- マスクしてをる人の眼を読みにけり ──上野泰『春潮』(1955年/昭和30年刊)所収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
今回、このように「マスク」を含んだ俳句を示しましたが、だからといって必ずしも「マスクを季語」と認めて作句したケースばかりではないかと思われます。ひょっとしたら「無季」の句だと本人は思っているかも知れませんし、「マスク」でない方が主たる季語と思っているかも知れません。
最新刊の一つ前の『角川俳句大歳時記』には、以下のような例句も記載されていました。いずれも平成以前の作句です。
いずれにしても大手の歳時記ですからちゃんと「マスク」を季語とした例句が記載されています。個人的には、3・4句目が特に好きなのですが、そしてこれらの句も「コロナ禍」前として詠んでも、「コロナ禍」後として詠んでも味わい深い普遍的な魅力がある作品群だと感じます。
ちなみに、直近の角川俳句大歳時記では、例句のラインナップが少し変わっていますので、ぜひ確認してみて下さい。いずれにしてもこの「普遍性」と「季節感」の同居が季語としての作句の鍵でしょう。
最後にご紹介したいのが、平成の最後に「プレバト!!」で登場した【村上健志】永世名人の特待生昇格を決めた78点の秀逸句です。タイミングとしては、2016年(平成28年)ですからコロナ禍の前です。
1位78点『テーブルに君の丸みのマスクかな』/村上健志
この句について、2021年10月22日(令和3年=コロナ禍が始まって1年半)に、村上健志さんと千原ジュニアさんがYouTubeで対談し、少し触れています。(↓)
ここでいった議論が素直な本音なのだと思います。「マスク」を季語として扱って良いのか分からない。コロナ禍前に作った過去の作品の、詠み方が変わってきていて、それも一種の時代の流れ。それを止めることは出来ないというのが「マスク」を詠んだ俳句・俳人が晒される宿命となっているのです。
【まとめ】結論を出すにはまだ早い。だからこそ?
なんて難しく言いましたが、まだ結論が出切っていない時代ですから、後はもう俳句を作ったり、俳句を読んだり貴方次第です。加えていえば、コロナ禍を経て、マスクが季語であろうと季語でなかろうと『普遍性』か『季節感』を備えた作品であれば名作として語り継がれるでしょう。
結論が出ていないことにある種甘えて、どっちの立場からでも良いから皆さんなりの「マスク×俳句」を時代の中で捉えていって頂きたいと思います。皆さんはどう考えますか? 考え方は変わりましたか? もし作句されている方もコメント欄にお寄せ頂ければと思います。
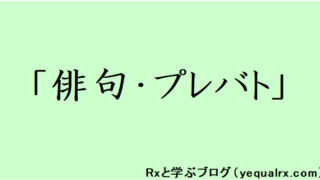
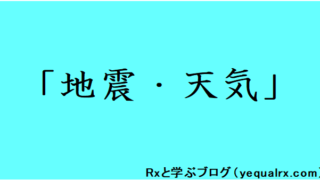
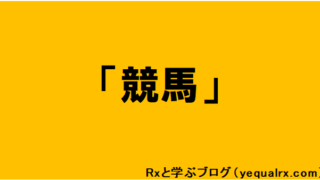
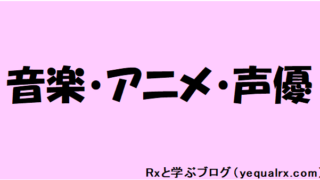
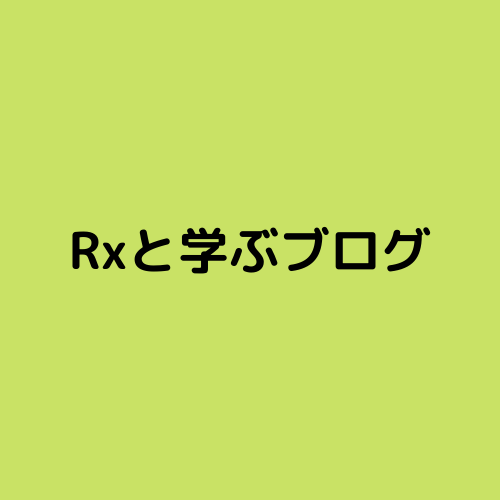






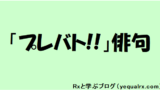
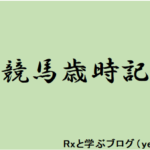

コメント