【はじめに】
重賞競走の歴史を振り返りながら季節の移ろいを感じる「競馬歳時記」。今回は「ジャパンカップ」の歴史をWikipediaと共に振り返っていきましょう。
ジャパンカップは、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)である。英称の頭文字から、JCという略称も用いられることがある。
正賞はロンジン賞、日本馬主協会連合会会長賞、東京馬主協会賞。
ジャパンカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
海外との交流100年・「ジャパンC」前史
「ジャパンC」が創設されたのは1981年のことであり、国際招待競走の検討は1970年代からだと一般には言われています。しかし、日本語版ウィキペディアなどの記載などをみても、断片的に海外との交流の歴史が窺えます。時代で区切ってざっくり見ていきましょう。
幕末・明治:ジャパンポニーから日露大競馬会のスイテンまで
幕末・居留地競馬として始まった日本の洋式競馬は、体格や馴致・気性面に劣る日本馬(ジャパンポニー)が中国馬(チャイナポニー)に差をつけられて始まりました。そのため、日本馬と中国馬でレースを分けて開催し、数少ない混合競走で日本馬は中国馬に惨敗を喫するのが常でした。だからこそ、日本馬のうち傑出した存在が中国馬などを下したり善戦した時は、当時の競馬ファンを熱狂させたのです。
その後も、日本馬は在来種と外来馬の混合馬が誕生したり、中国馬以外の諸外国の馬も輸入されたりと競馬の中心的な存在はバリエーションに富んでは淘汰されていきましたが、明治時代を通じて日本馬が一枚劣るという見立ては続きました。
広く知られた話としては、明治中期の2度の戦争(日清・日露)で西洋列強の軍馬と日本の馬が大きく見劣ることが白日の下に晒されたため、馬品改良に努めるトレンドに転換しました。詳細は『豪サラ』のページや『小岩井農場の基礎輸入牝馬』などをご覧頂ければと思いますが、国・軍主導での日本馬の向上が推進された時代が確かにありました。
ミラや第二メルボルンはウィキペディアに単独記事があるほどに現代にまで名を残した豪サラで、その強さは当時としては圧倒的なものがありました。
また、1908年に馬券の販売が国内で中止された翌年(1909年)『日露大競馬会』が開催され、日本馬の【スイテン】がシベリア産馬に全勝したことは、日本最初期の海外遠征として知られています。
大正時代:コイワヰなどから国産馬も健闘の時代へ
明治時代や昭和時代は、父内国産というだけでレッテルが貼られるような時代であり、それほどに海外の一流血統馬との力量差が如実な時代だったと伝わります。そもそも外国調教馬を招く必要もなくその出自だけで混合競走を安易に組めないほどの力量差があったのです。
しかし、明治時代には血統も分からないような馬が多くいた所から、大正時代を通じていわば「血統書付き」のような軽種馬が大レースを独占するようになると、数代前に海外から輸入したけれどその後は日本で繁殖していた馬の占める割合が増えていくこととなります。
大正時代の中期まで活躍した【コイワヰ】(酷量の中82戦45勝)自身は持込馬だったものの、その産駒が1920年代に活躍しだし、『小岩井農場の基礎輸入牝馬』牝系と共に日本産馬の向上に繋がりました。
明治の終わりに始まった通称「連合二哩」というビッグレースの正式名称は、当初『優勝内国産馬連合競走』であり、その名の通り内国産馬のチャンピオン決定戦でした。昭和の日本ダービーに似た存在です。
なお、ここまで語った内容は、戦後日本の範囲内での概念ですが、戦前の旧・外地という所まで触れると、横浜競馬のような国際色豊かな洋式競馬が各地で催され、日本以上にオープンな競馬が開催されていたことも付け加えておきましょう。(ウィキペディアのリンクは以下のとおり)
旧外地:樺太 満洲国 関東州 朝鮮 台湾
昭和時代:戦後は徐々に内国産馬保護の時代に
昭和1桁台になると『下総御料牧場の基礎輸入牝馬』が相次いで導入されると共に、ヨーロッパを中心とした種牡馬も輸入され、小岩井系から発展しすっかり日本産馬として定着していた馬たちとの配合が進んでいきます。
折しも、日本競馬会への統合や日本ダービーを始めとするクラシック競走の創設が続き、戦前は、父・輸入種牡馬、母系・基礎輸入牝馬という血統表の馬が大レースを多く占める結果となりました。
例外的に、名馬・クモハタの姉であって繁殖牝馬・月城としても活躍した【クレオパトラトマス】が、戦前に海外遠征を画策したという記載を見たことがありますが、戦争によって頓挫してしまいました。
戦後に入ると、軍馬改良といった大義名分がなくなる一方で、経済復興と娯楽としての面で競馬は復活をはかることとなっていきます。人間のみならず馬資源も手薄な競走馬不足を補う意味で、明治期とは違った背景をもった『豪サラ』が導入されていきます。
この頃、豪サラは下級で独自の競走が組まれ、オープンクラスでも出走できるレースは限られていましたが、20世紀のような内国産馬を壊滅させるほどの実力差はありませんでした。
そんな1950年代には【トキノミノル】が無事ならば海外遠征を強行していたかも知れません。
しかし1960年代に入ると、日本馬が国際招待競走の先駆け「ワシントンDCインターナショナル」へと挑戦するも大敗続き。1959年の米でのハクチカラや1967年の仏でのフジノオーは極めて例外的な優勝であるなど、日本調教馬が一線級であっても海外では通用しない時代というのが昭和中期でした。
持込馬(もちこみば)とは、かつて中央競馬で用いられていた競走馬の区分。母馬が胎内に仔馬を宿した状態で輸入され、日本国内で産まれた馬、または仔馬が満1歳を迎えるまでに母馬とともに輸入された馬のことを指す。
もともと持込馬は内国産馬扱いであり、天皇賞やクラシックへの出走制限は行われていなかった。しかし、それまで許可制であった活馬(生きている馬)の輸入が自由化された1971年、その見返りとして内国産馬振興の方針が打ち出され、その一環として1971年6月30日以降に輸入された繁殖牝馬から生まれた仔馬は外国産馬とほぼ同等の扱いを受けることとなり、クラシック5大競走、並びに天皇賞においては持ち込み馬の出走も全面的に禁止されてしまった。競馬新聞などの馬柱には○の中に「持」のマークで持込馬であることが表記されていた。
この制限は1983年一杯で廃止され、元のように内国産馬としての扱いを受けることとなった。
持込馬
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
内国産が種牡馬として冷遇されていき、輸入種牡馬が重用された昭和中後期において、外国産馬は当然と見做され、そして上記の持込馬でさえも『出走制限』が掛けられていたことは21世紀に競馬を知った人々にとってはむしろショックかも知れません。
しかし、そうしなければならないほどの実力差が(時に)あったことは、ウマ娘でも話題となったスーパーカーこと【マルゼンスキー】の強さをみれば明らかでしょう。
1970年代には一旦、強い保護主義的な方面に偏りましたが、それによって日本馬は(100年前ほどではないかも知れませんが、)外の血統を持つ馬と対戦し力の差を図る機会に恵まれなくなっていました。表面的には日本馬の力を図りきれない中で1980年代を迎えることとなったのです。
昭和時代:日本2-6海外
そうした歴史の流れの中で、1981年に実現したのが「ジャパンC」でした。天皇賞(秋)を1ヶ月前倒しし、海外馬を迎える変革を遂げての第1回開催は、今でも語り継がれています。
歴史
1970年代後半より「世界に通用する強い馬づくり」が提唱され、日本国外の調教馬を招待して国際競走を開催する計画も持ち上がっていたが、招待馬の選定にあたりJRAと各国との意向に齟齬があり実現しなかった経緯がある。1981年に日本初の国際招待競走として、ジャパンカップが創設された。第1回は北アメリカとアジア地区から招待馬を選出したが、翌年からは招待範囲がヨーロッパ、オセアニアにも広げられ、参加国の多さから「世界一の競走」「競馬のオリンピック」と評されることもあった。さらに1983年からは、地方競馬の所属馬も招待対象に加えられた。
第1回の優勝馬・メアジードーツは、アメリカからやってきた成績の目立たない牝馬の上、当時のコースレコードを1秒更新したことから、日本の競馬関係者に「(日本馬は)永遠に勝てないのではないか」と思わせる衝撃を与えた。そうした懸念は極端なものであったが、創設から1990年までの10年間は外国招待馬の8勝に対し、日本馬はカツラギエース(1984年)とシンボリルドルフ(1985年)の2勝にとどまり、外国招待馬の活躍が目立っていた。
ジャパンカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
その第1回の結果については、以下のとおり纏められています。文字通りの「JRAの完敗」でした。
競走内容
ゴール手前でメアジードーツがフロストキングを差し切って1着。ザベリワンは3着まで。4着にペティテート。日本馬はゴールドスペンサーの5着が最高であった。ゴールドスペンサーは地方競馬出身であり、JRA生え抜きの馬はホウヨウボーイの6着が最高という結果となった。勝ち時計2:25.3秒は、エリモジョージの2:25.8秒をコンマ0.5秒上回る日本レコードで決着。4着までの外国馬が当時の日本レコードを上回った。これ以後、2018年のジャパンカップでアーモンドアイが従来のレコードを更新するまで、日本の2400mレコードはジャパンカップに来日した外国馬によって更新され続けた。
第1回ジャパンカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
以下、昭和時代の勝ち馬をリストアップしましたが、海外馬6勝、日本馬2勝という成績が示す通り、当時は一線級の日本馬が準一流の海外馬に太刀打ちできないというのが大方のトレンドでした。
| 回 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1981年 11月22日 | メアジードーツ | 牝5 | USA | 2:25.3 | 5 |
| 第2回 | 1982年 11月28日 | ハーフアイスト | 牡3 | USA | 2:27.1 | 6 |
| 第3回 | 1983年 11月27日 | スタネーラ | 牝5 | IRE | 2:27.6 | 3 |
| 第4回 | 1984年 11月25日 | カツラギエース | 牡4 | JRA | 2:26.3 | 10 |
| 第5回 | 1985年 11月24日 | シンボリルドルフ | 牡4 | JRA | 2:28.8 | 1 |
| 第6回 | 1986年 11月23日 | ジュピターアイランド | 牡7 | GBR | 2:25.0 | 8 |
| 第7回 | 1987年 11月29日 | ルグロリュー | 牡3 | FRA | 2:24.9 | 3 |
| 第8回 | 1988年 11月27日 | ペイザバトラー | 牡4 | USA | 2:25.5 | 9 |
そして振り返ってみると2番人気以上での優勝は日本の三冠馬・シンボリルドルフのみであり、その他は3番人気以下。戦前の予想以上に激走する海外馬が多かったという見方もできそうです。
当時はヨーロッパのみならず、北米に南半球にと国際色豊かなメンバーが揃っていましたが、日本国内でも「地方枠」が設けられ、ロツキータイガーが2着に入るなど、いま以上に『競馬の祭典』といった盛り上がりを見せていた印象です。
なお世界に目を向ければ、1984年に「ブリーダーズカップ・ターフ」が創設され、欧米の一流馬を招待したい時期に、より華やかな舞台が出来てしまったことは見過ごせない事実だったと思います。
平成年間:日本22-8海外(通算24-14)
ここから時代は「平成」に入ります。平成15年(2003年)までを平成前半、平成16年からを平成後半としたいと思います。
平成前半:日本8-7海外(通算10-13)
平成元年は、ニュージーランドのホーリックスが日本のオグリキャップを、世界レコード(2.22.2)で制する伝説のレースに始まります。そして1990年にもオーストラリアの馬が勝って、2年連続・南半球の馬が制する華やかさを見せます。更に、ゴールデンフェザントがアメリカ馬として最後の優勝を果たして海外勢が3連勝としています(この段階で2対11)。
1992年に国際G1となった年に日本の【トウカイテイオー】が父以来7年ぶりにジャパンCを制すると、続く2年は日本馬が勝利。気づくと平成に入って、「外外外日日日外外外日日日日外日」という極めて拮抗した時代を迎えていきます。15年戦って8勝7敗、1980年代を思えば日本馬の大躍進です。
| 第9回 | 1989年 11月26日 | 東京 | 2400m | ホーリックス | 牝6 | NZL | 2:22.2 | 9 |
| 第10回 | 1990年 11月25日 | 東京 | 2400m | ベタールースンアップ | セ5 | AUS | 2:23.2 | 2 |
| 第11回 | 1991年 11月24日 | 東京 | 2400m | ゴールデンフェザント | 牡5 | USA | 2:24.7 | 7 |
| 第12回 | 1992年 11月29日 | 東京 | 2400m | トウカイテイオー | 牡4 | JRA | 2:24.6 | 5 |
| 第13回 | 1993年 11月28日 | 東京 | 2400m | レガシーワールド | セ4 | JRA | 2:24.4 | 6 |
| 第14回 | 1994年 11月27日 | 東京 | 2400m | マーベラスクラウン | セ4 | JRA | 2:23.6 | 6 |
| 第15回 | 1995年 11月26日 | 東京 | 2400m | ランド | 牡5 | GER | 2:24.6 | 6 |
| 第16回 | 1996年 11月24日 | 東京 | 2400m | シングスピール | 牡4 | GBR | 2:23.8 | 4 |
| 第17回 | 1997年 11月23日 | 東京 | 2400m | ピルサドスキー | 牡5 | GBR | 2:25.8 | 3 |
| 第18回 | 1998年 11月29日 | 東京 | 2400m | エルコンドルパサー | 牡3 | JRA | 2:25.9 | 3 |
| 第19回 | 1999年 11月28日 | 東京 | 2400m | スペシャルウィーク | 牡4 | JRA | 2:25.5 | 2 |
| 第20回 | 2000年 11月26日 | 東京 | 2400m | テイエムオペラオー | 牡4 | JRA | 2:26.1 | 1 |
| 第21回 | 2001年 11月25日 | 東京 | 2400m | ジャングルポケット | 牡3 | JRA | 2:23.8 | 2 |
| 第22回 | 2002年 11月24日 | 中山 | 2200m | ファルブラヴ | 牡4 | ITA | 2:12.2 | 9 |
| 第23回 | 2003年 11月30日 | 東京 | 2400m | タップダンスシチー | 牡6 | JRA | 2:28.7 | 4 |
勝ち馬をみると、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリアと錚々たるパート1国陣営が勝ち馬に名を連ね、平成10年代に入ると『日本馬が上位独占!……上位は、全部ニッポン!』と実況をされた年を契機に完全に日本馬優位の時代を迎えます。
無視できないところとして「ジャパンC」の優勝賞金が2000年にほぼ倍増され、1.32億円から2.5億円と当時としては破格の金額となりました。また、同じアジアで香港国際競走が飛躍を始め、日本馬では【ステイゴールド】が香港ヴァーズに挑戦したのがこの頃です。
平成後半:日本14-1海外(通算24-14)
日本馬が強くなった側面もあると思います。凱旋門賞やドバイ・香港で日本馬が好走することが増え、1990年代後半から始まった海外遠征での日本馬の活躍が平成後半にかけて花開いていきました。
とはいえ、2004年からの15年間で「日本馬が14勝」したという事実は、『ジャパンC』というレースの創設当時の意義が薄まり、国際レースとしての華やかさが弱まっていった一抹の寂しさをも感じる時代の変化だったとも言えるでしょう。
| 第24回 | 2004年 11月28日 | ゼンノロブロイ | 牡4 | JRA | 2:24.2 | 1 |
| 第25回 | 2005年 11月27日 | アルカセット | 牡5 | GBR | 2:22.1 | 3 |
| 第26回 | 2006年 11月26日 | ディープインパクト | 牡4 | JRA | 2:25.1 | 1 |
| 第27回 | 2007年 11月25日 | アドマイヤムーン | 牡4 | JRA | 2:24.7 | 5 |
| 第28回 | 2008年 11月30日 | スクリーンヒーロー | 牡4 | JRA | 2:25.5 | 9 |
| 第29回 | 2009年 11月29日 | ウオッカ | 牝5 | JRA | 2:22.4 | 1 |
| 第30回 | 2010年 11月28日 | ローズキングダム | 牡3 | JRA | 2:25.2 | 4 |
| 第31回 | 2011年 11月27日 | ブエナビスタ | 牝5 | JRA | 2:24.2 | 2 |
| 第32回 | 2012年 11月25日 | ジェンティルドンナ | 牝3 | JRA | 2:23.1 | 3 |
| 第33回 | 2013年 11月24日 | ジェンティルドンナ | 牝4 | JRA | 2:26.1 | 1 |
| 第34回 | 2014年 11月30日 | エピファネイア | 牡4 | JRA | 2:23.1 | 4 |
| 第35回 | 2015年 11月29日 | ショウナンパンドラ | 牝4 | JRA | 2:24.7 | 4 |
| 第36回 | 2016年 11月27日 | キタサンブラック | 牡4 | JRA | 2:25.8 | 1 |
| 第37回 | 2017年 11月26日 | シュヴァルグラン | 牡5 | JRA | 2:23.7 | 5 |
| 第38回 | 2018年 11月25日 | アーモンドアイ | 牝3 | JRA | 2:20.6 | 1 |
海外勢が最後に勝ったのは、2005年の【アルカセット】。この時は日本の【ハーツクライ】がハナ差迫るも届かず、勝ちタイム2分22秒1は1989年のホーリックス対オグリキャップを連想させるには十分なドラマチックな内容でした。
しかしこの時は、これが(平成)最後の海外馬の勝利になるとは思えなかったと思います。事実、当時の海外勢は2分22秒台という破格のタイムについていっていました。アルカセットが優勝し、ウィジャボードは5着、バゴが8着であり、ヨーロッパの馬も対応できていたからです。
それが徐々に海外馬の出走頭数も減り、活躍できる比率も落ちていきます。そして本来、馬場適性の面でいうならば適性がありそうな「アジア・北米」勢はジャパンC以外のレースを選択するようになった結果、半ば『海外馬は前提として消し』が馬券を狙う上での鉄板の消去法となっていったのです。
ジャパンCで日本馬が活躍してくれることは嬉しい反面、国際的な魅力や地位の低下の反動は数年から十数年のスパンを置いて遅れてやってきます。
平成最後の2018年に【アーモンドアイ】が2分20秒6という日本国内もドン引きするような世界レコードが叩き出されたことは、高速馬場を主戦場としていないヨーロッパ勢(ジャパンCに積極的に出走してくれていた)を敬遠させるには十分過ぎるものでした。
令和時代:日本3-0海外(累計27-14)
そして、令和元年の「ジャパンC」は、史上初めて外国調教馬の出走なし(全馬辞退)となりました。
ジャパンカップ創設以来初めて外国調教馬の出走がなく、すべて日本調教馬の15頭による競走となった。
ジャパンカップ直前の11月22日、東京都港区のコンラッド東京で180人の世界13か国の競馬主催者、出走馬関係者を招いてウェルカムパーティーが行われた。
第39回ジャパンカップ
パーティーの始めにJRAの後藤正幸理事長は、外国調教馬が不在のジャパンカップとなった理由として「検疫の問題」「馬場構造の違い」「各国主催者間の競争の激化」「日本(調教)馬の資質の向上」を挙げるスピーチを英語で行った。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

海外馬敬遠の原因は一つでなく、様々あることが日本の競馬ファンに改めて認識されるに至りました。こうした結果、令和の時代は『ジャパンC』が、そして日本競馬が世界の中の国際招待競走として復活を懸けるべく諸問題を解決しなければならないフェーズとなっていったのです。諸問題については前述のウィキペディア『第39回ジャパンカップ > 議論』をご覧ください。
| 第36回 | 2016年 11月27日 | キタサンブラック | 牡4 | 2:25.8 | 1 | 3億円 | 119.50 |
| 第37回 | 2017年 11月26日 | シュヴァルグラン | 牡5 | 2:23.7 | 5 | 3億円 | 121.25 |
| 第38回 | 2018年 11月25日 | アーモンドアイ | 牝3 | 2:20.6 | 1 | 3億円 | 122.50 |
| 第39回 | 2019年 11月24日 | スワーヴリチャード | 牡5 | 2:25.9 | 3 | 3億円 | 118.00 |
| 第40回 | 2020年 11月29日 | アーモンドアイ | 牝5 | 2:23.0 | 1 | 3億円 | 124.50 |
| 第41回 | 2021年 11月28日 | コントレイル | 牡4 | 2:24.7 | 1 | 3億円 | 121.25 |
2016年以降のレースレーティングと合わせて表を引用しました。2019年は外国馬不在でレース自体もレースレーティング118.00と凹んでしまいましたが、その翌年2020年は一転して『124.50』という世界的にみても最高水準の高レートとなりました。日本の三冠馬3頭が激突し、アーモンドアイが芝G1で9勝目をあげる歴史的な快挙を遂げたあのレースです。
しかしこのレーティングにはからくりが一つあって、日本馬がドバイや香港で活躍するようになり、基準となる一部の日本馬のレーティングが向上したことによって全体が引っ張られた側面も否めません。故に、本質的なメンバーの充実とは別に、日本国内馬が活躍するレースでも国際的なレーティングが高まる現象が起きている点も抑える必要があるでしょう。
そして日本国全体にも言えるかも知れませんが、昭和・平成(主に20世紀)までに培ってきた伝統が、令和に入って剥落し、それを再考して復活させる営みが必要となる時代となっていきました。為替面での日本の相対的地位の低下、国際競走の増加による国内外馬の別レースの選択といった課題は、それ以前から前兆があったものの、コロナ禍などによって一気に表面化したのです。
もちろん、JRA(日本中央競馬会)も、2020年代に入って(遅まきながら)幾つかの施策を打ち出し、それを実践することによって海外勢の参戦が少しずつ戻ってきたことは喜ばしいことでしょう。
外国馬の参戦について
ジャパンカップを含む一連のジャパン・オータムインターナショナルシリーズの直後に、香港国際競走が行われ、そちらへ外国調教馬の参戦が多くなりつつあり、実際ジャパンカップは2019年の開催で外国馬の参加が一頭もないという異常事態となったことを踏まえ、2021年6月28日に日本中央競馬会関西定例会見(大阪市)の席で、「これまで、外国馬の関係者からは、帯同馬を連れていきたいが、走るレースがないと聞いたことがあったのです。今はジャパンカップの前日に「キャピタルステークス」がありますが、今年(2021年)から、外国馬の大量参戦を促すために、ジャパンカップが開催される週に、賞金条件戦クラスで国際競走を新設する」ことを目指すと、国際・競走担当理事の臼田雅弘が明かした。そして2021年8月1日に発表された「令和3年度秋季競馬番組」において、調教などで帯同する予定の馬の出走機会を拡大しつつ、ジャパンカップに出走を予定する外国馬がジャパンカップに出走しやすい環境を提供することを目指し、次の競走を国際競走に指定することになった。
さらに、外国馬はこれまで、競馬学校(白井市)か、三木ホースランドパーク(三木市)の国際厩舎で原則1週間程度の検疫を受けなければならなかったが、より一層の外国馬の参戦を促す観点から、東京競馬場内馬場内に、国際厩舎の建設を行うことになった。これは諸外国においてはレースが開催される競馬場内での検疫が行われるのが通例であり、その流れを受けてのものである。2022年5月末に完成し、秋競馬には運用できる予定である。これにより、外国馬は国際厩舎6棟・最大12頭が検疫を受けながら、競馬場で直接調整できるようになるという。
ジャパンカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2022年に海外馬が4頭出走しましたが、これに『国際厩舎の建設』が大きなプラスだったとの報道がありましたが、こうして『国際招待』を銘打つならばやはりある程度、海外陣営の要望を取り入れる必要はありましょう。賞金面では、2022年に4億円、2023年には5億円と伸ばし、報奨金を積んでいるにも拘らず、マネー以外の理由で他のレースを選択する陣営が多い時点で、構造的なウィークポイントがあるに違いないからです。
本当に『国際招待競走』として「ジャパンC」を続けていくならば、招待したい側に真摯に耳を傾け、できうる範囲で対応しなければいけないでしょう。ひょっとしたら「秋・11月開催」や「東京開催」も「2400mというクラシックディスタンス」も、1981年当時(今から40年以上前)に決めた条件自体が今「国際招待競走」として相応しいものと限らないかも知れないからです。仮にJRAがこの条件を堅持したいならば、それは海外勢に条件を強いることに繋がるものであり、離れていくのは当然でしょう。
令和の時代、そして2020年代は『ジャパンC』の分岐点とも言える重要な時期だと個人的には考えています。今よりも環境が改善していくとは考えにくいでしょう。新たな海外G1が創設され、相対的な地位が更に低下することも考えられます。そうした中で、JRA、海外陣営、そして我々競馬ファンが、どういうジャパンCに望みを持っていくのか、注目していく必要があろうかと思います。
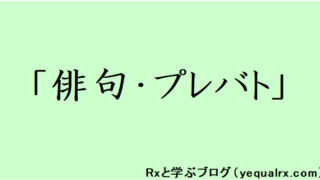
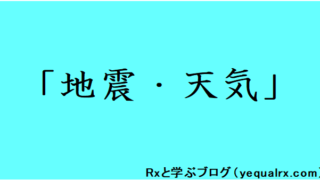

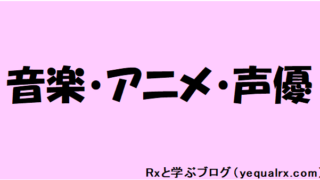





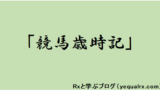


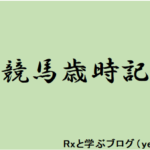
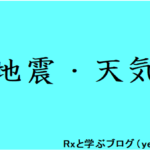
コメント